 |
早稲田大学 |
早稲田大学所沢校地B地区に現存する湿地は、狭山丘陵において最大規模を有し貴重な動植物が認められる、保全上の重要性が高い自然環境となっている。しかしながら、水田耕作の放棄等の要因にともない乾燥化が年々進み、水生動植物等の減少も見られる。こうした背景を受け、環境・健康・福祉等の分野を対象とした研究機関の建設を所沢校地B地区で進めるに際し、早稲田大学は以下の方針に基づき、湿地の重要性を損なわないための環境管理に取り組んでいくものとする。
|
※「平成14年度第1回早稲田大学所沢校地B地区自然環境評価委員会」平成14年5月15日にて策定 |
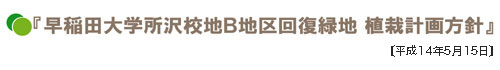 |
早稲田大学 |
早稲田大学所沢校地B地区は、全域が「県立狭山自然公園」内に位置する、豊かな自然環境に恵まれた地域に立地している。早稲田大学は、今後B地区において環境・健康・福祉等の分野を対象とした研究機関の建設を進めるに際し、自然環境との十分な調和を図るために、以下の方針に基づく「回復緑地」の植栽計画の検討・実施に取り組んでいくものとする。
|
※「平成14年度第1回早稲田大学所沢校地B地区自然環境評価委員会」平成14年5月15日にて策定 |
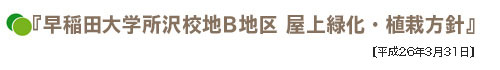 |
早稲田大学 |
| 早稲田大学所沢校地B地区は、狭山丘陵最大規模の湿地が現存することや敷地全域が県立狭山自然公園内に位置する豊かな自然環境に恵まれていることから、これまでに「早稲田大学所沢校地B地区 湿地環境管理方針」および「早稲田大学所沢校地B地区 回復緑地植栽計画方針」が策定され、生物多様性や景観に最大限配慮した校地の建設計画が進められてきた。 研究棟上部の屋上についても、オオタカ保護対策や周辺の丘陵地景観との調和等の観点から緑化・植栽が取り組まれてきたが、一定期間を経て近年の気象条件等の要因に基づく生育状況の不安定化が顕著な現状がモニタリングにより明らかになっている。そうした背景を踏まえ、これまでに策定されている上記の方針との整合の基に、屋上緑化を改めて推進するうえで留意すべき事項を、以下の屋上緑化・植栽方針としてまとめ、植栽管理計画の検討・実施に取り組んでいくものとする。
|
※「平成25年度第2回早稲田大学所沢校地B地区自然環境評価委員会」(平成26年3月31日)にて策定 |